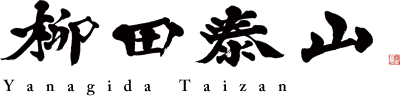本日の書
2016年11月30日 0:01

翰墨結縁(かんぼくけちえん)と言う言葉がある。
まさに「書」によって結ばれる人とのご縁である。
どれだけご縁を戴いた方に救われたか。
また、一本一本の線にも縁がある。
新しい線との出会いがある。
「人」と「線」そして「自分」。
やはり「書」に感謝であろう。
老泰
2016年11月20日 16:10

数年前に書いた小品である。
この「鷹」という字には横の線が十本ある。この一本一本の線の角度に細心の注意を要する。
実は、一番上にある長い横画が一番右上がり、下に下がるにつれ平に近い角度となる。但し「鳥」の烈火(四つの点)があるので、微妙なバランスを考えないといけない。楷書の厄介なところで、決して気分だけで書けないのが辛い時もある。然し、その微に入り、細に入りが魅力でもある。針の穴に糸を通す如く書くのも「書」の技である。
老泰
2016年11月11日 0:01

最近の「書」には額装、軸装に神経を使わなくなった。
馬子にも衣装が無くなってしまった。
と同時に、裏打ちの時、作品そのものに墨が腐っていて、汚れたまま表具してしまう輩がいる。
これには耐えられない。
「書」はどこまでいっても神経を使わなければいけない。
老泰
2016年11月1日 0:00

時々、ガツンと書きたくなる。だからと言って、むやみやたらと書いてはいけない。楷書美学の追究が必要。
その楷書美学とは何だろう。まだまだ、何かを欲している状態である。
まるで龍門の前に立っているようなもの。一歩踏み入れる事が…。
門の中には何があるんだろう。
老泰
2016年10月20日 12:00

巖は高い巌(いわお)。
邃は奥深い。
巖邃は険しい山に奥深い洞窟がある。転じて険しく深いと意味される。この言葉は楷書に適しているだろう。線質の奥深さと、崇高な楷書を求めているつもり。。しかしまだ五合目くらいか。
「書」は厳しくなればなる程、良いものが書けると信じている。徹底的に悩むべきであろう。これで良しと思ったら駄目になり、所詮、小さな山にすぎない。
老泰