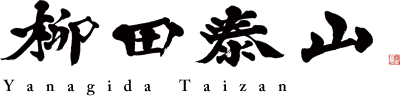本日の書
2019年5月20日 20:06

仏語では、真如(あるがままにある状態のこと)の永遠なる自在の働き。
狭い見解や執着から離れた自由自在の悟りの境地。との説明がある。
ただ、この様に「書」として揮毫すると、煩悩の塊となってしまう。
素直にありのままに書く事は難しい。最近、「書」の難しさに直面させられている。
老泰
2018年3月1日 8:59
.jpg)
志を抱いて、時節の到来を待つこと。
魚が鱗を休め、鳥が翼を静かに収めていると言う意味。
楷書として「戢」の「弋」の上から下の斜めの線(斜画・しゃかく)が非常に難しい。上手く書けば、かなり美しいものになるが…。楷書書きは一点一画に細心の注意をはらわなければいけない。
老泰
2018年1月31日 3:48

貴殿のこの祝いの日に、福寿を祈る星が北の空にひかる。
金の香炉に香り高い香を薫じ、そのまわりを輝かそう。
気高い山のように千年もすがすがしく、海の如く万年も清らかであれ。
君の為に、この八句の詩を捧げ祝おう。
そして蓬莱山の不老不死の仙人の寿を授からんことを祈る。
この詩の作者・嘉靖主は、中国の明代・嘉靖期の主、つまり嘉靖帝のことである。明の第十二代皇帝で、世宗(せいそう)と言う。自身の男児誕生を祝って詠んだ詩と思われる。
扇面作品は厄介なもの。「書」で言えば、行書・草書・隷書・篆書では面白く書けるが、楷書となるとその様な訳にはいかない。どんな紙面であってもそれに合わせた字形(結構美)を追究しなければ、楷書作品とは言えないであろう。
老泰
2017年3月31日 16:42

法華経・観世音菩薩普門品の中の語句。福徳の集まることが海のように広大であるということ。
経文を書くときは、いつも緊張する。確かに漢詩漢文でも緊張はあるが、殊に経文は一種独特の重みを感じてしまう。
「書」は常に緊張の連続である。現代は「書」を楽しむという立場もあるが、それでは決して、高い境地は望めない。芸術とはそういうものである。精神的、宗教的思想が入らなければならない。
肩肘張った、ものの言い方かも知れないが…。
老泰
2017年3月11日 12:40

ある時は龍となって天を駆け、
ある時は蛇となって泥沼をはう。
時の動きにつれて治世にはあらわれ、
乱世には潜むことをいう。
今は「蛇」なのか?
老泰